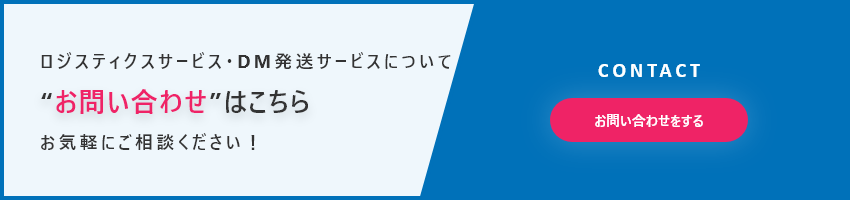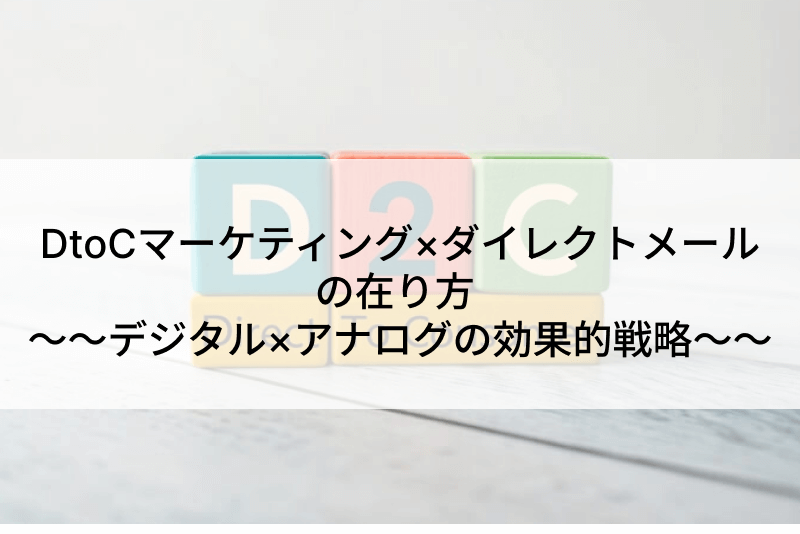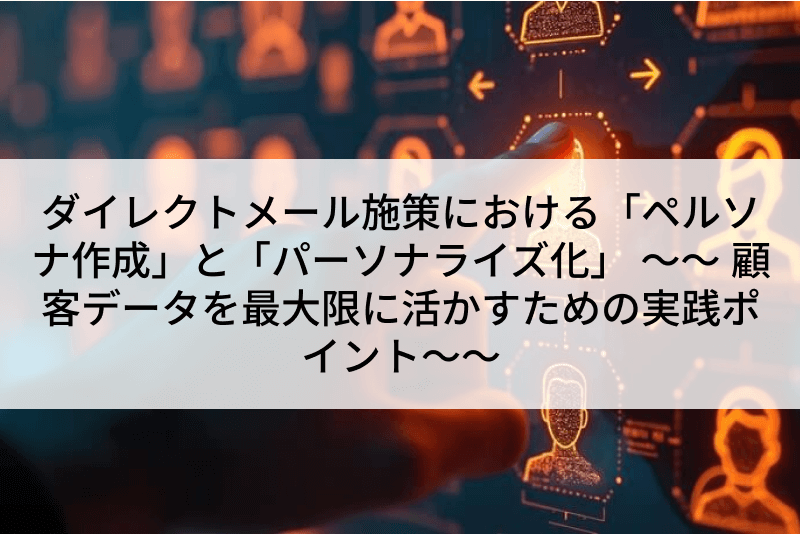近年、デジタルマーケティングに依存している企業が、ほとんどを占めています。
競合がそうしているから、自社もデジタルマーケティングに依存するという姿勢は正しいのでしょうか?
実際問題、デジタルマーケティングがZ世代に有効的戦略だとしても、デジタルマーケティングもマーケティング手法のひとつに過ぎないのです。
デジタルマーケティングが使い物にならない戦略であるとは言うつもりは毛頭ありません。
ただし、全面的にデジタルマーケティングに依存してしまうのではなく、今だからこそ、デジタルマーケティングと、アナログマーケティングの融合を取り入れたZ世代戦略を行うべきです。
目次
デジタルマーケティングとアナログマーケティングの意味
マーケティング業界で名が知られているフィリップ・コトラーですが、彼の著書である「マーケティング4.0」では、「オンラインの世界とオフラインの世界は、ゆくゆくは共存し、融合するだろう」という意味深い発言をしています。フィリップ・コトラーの発言を借りれば、理想とする顧客体験を実現するためには、デジタルとアナログの組み合わせが重要だということです。
また、日経BPコンサルティングが大手企業を対象に実施した調査においては、デジタルの組合せを既に実施している企業は31.5%存在しています。実際に効果が出たと答えた企業も63.1%の数値です。
他社も同様にして、デジタルマーケティングに全面的に傾倒……。もうそんな時代でもなくなってきているのです。
時代は確実に、デジタルに流れているという思いは、多くの方々がまだお持ちでしょう。
それでもデジタルとアナログの組み合わせが高い効果を発揮できるのは、顧客自体がずっぽりとデジタルに依存しているわけではなく、デジタルとアナログのはざまを行ったり来たりしているからです。
メールだけでは、リアルと比較して顧客のモチベーションがアップしにくい
顧客が、商品やサービスを購入するに至るまでのプロセスは、大きく分類すれば、認知、興味・関心、比較・検討、商談と言った感じになるでしょう。この様々なプロセスにおいて、顧客はデジタルチャネルにだけ接触しているわけではありません。デジタルマーケティングの手段であるメールは、追客を担うとても大事なチャネルとしてとらえることができます。有能なMAツールを活用し、ユーザーの属性や行動に合わせたシナリオを設定してメール送信をしている企業もあることでしょう。
ただし、それでも、商品・サービスの良さを、顧客に100%理解してもらうのにはメールでは不十分です。メールだけの手段に依存するのでは、リアルと比較して、顧客のモチベーションがアップしにくいからです。
実際に、リアル中心に営業が行われれば、顧客とのコミュニケーションを通じ契約獲得をしているため、実際に商品・サービスの良さを伝え、かつ、顧客の疑問や不安にタイムリーに応えることができ、また、営業マンの熱意も一緒に伝えることができるでしょう。
メールがフル稼働したとしても、また、タイトルや文言の調整をして改善を試みたとしても、そこに期待できる効果は限定的と言うべきです。
アメリカのコーネル大学が実施している調査では、メールで行うコミュニケーションよりも、面と向かって伝える戦略が34倍も効果的だという報告もあります。
このような調査の結果を見ても、デジタルを過信しすぎることも危険です。人々が、実感を感じるのも、デジタルだけでは不十分と言えます。
ただし、それぞれ顧客がデジタル上で情報収集することがいまだメインになっていることも事実であるため、デジタル上での施策を中断するような問題でもありません。
顧客に提供できる購買体験に関しても、デジタルではできることに限界があると考えるべきです。たとえば、リアルなイベントを開催することで、顧客購買にそうとう良い影響を与えることができるのではないでしょうか。
デジタルマーケティングが停滞している理由
デジタルマーケティングは、デジタルを活用したマーケティング手法であり、Webサイトであったり、SNS、LP、DMP、マーケティングオートメーション、PR動画……などと言った様々な手段を活用することができます。しかし、日本ダイレクトメール協会の調査によれば、デジタルへの興味が下がる高齢の方々にとって、いまだ紙媒体の影響力は絶大です。
それだけでなく、紙媒体のダイレクトメールの発送は、デジタル時代の中で完全に育ったZ世代の方々にも影響があるということがわかっています。
デジタルネイティブの壁
令和4年度の総務省のデータを確認すれば、Z世代にあたる10代、20代の人たちは、全年代の中でも、ネットを利用する時間がもっとも長く、一方でテレビや新聞、ラジオに関わる時間はかなり減少しています。デジタルネイティブとも呼ばれているように、SNSやインターネットが身近にある中で生まれ育った以上仕方のないことですが、情報を収集することやショッピング、オンラインスクール……など幅広い用途で、スマホやタブレットを使用することがごくごく当然となっている世代です。
Z世代の人たちは、商品・サービスを購入するときにSNSで情報収集をする傾向が顕著にあります。SNSでは写真や動画だけでなく、実際にお客様が使った感想や口コミといった実体験の有益な情報を得ることができます。
しかし、デジタルで育ったZ世代は、感情の乏しい画面越しの情報に飽きがきており、紙媒体の手段が新鮮に見える事態が起きているとも言われています。物心がつく頃からデジタルが身近な存在として当たり前になっているからこそ、紙媒体の側にある、あたたかみに価値観を感じるようです。
オンライン上の情報が飽和状態にある時代だからこそ、“あたたかみ”のあるアナログ体験が、新鮮な価値として受け入れられ始めています。
アナログには信頼感がある
現在では多くの申請方法がオンラインで完結できる便利な時代となりました。しかし、一方では、たとえば2020年の10万円の給付金の場合、多くの人たちがオンライン申請ではなく、封書申請を使用しています。マイナンバーカードの手続きでも、多くの人たちが紙媒体での封書申請を選んだという事実があります。
それは何故なのでしょうか?
やはり紙媒体には圧倒的な信頼感があるからと言っていいのではないでしょうか。
ネットで、個人情報を入力し申し込みをし、果たして信頼できる場所へ確実に届くのか……、人たちはデジタルの信頼性にいささか不安な印象を持っているのです。
アナログは、特別感を感じさせる手段である
一般社団法人日本ダイレクトメール協会の「ダイレクトメールメディア実態調査2022」の調査によれば、本人宛のダイレクトメールの閲読率は7~8割とそうとう高く、特にZ世代に該当する20代の人たちの場合は、ダイレクトメールを閲読した後の行動率が高いという結果報告が出ています。Z世代は、特にパーソナライズされた情報に関心をもち、自分だけの情報という特別感を好む傾向にあると言っていいでしょう。
Z世代への紙媒体のダイレクトメール発送を成功させるポイント
いま、Z世代マーケティングが注目されている大きな理由として、Z世代の持つ情報の発信力・拡散力の高さがあります。現代社会の若い人たちはSNSを通じてお互いの個性を認め合い、自力で発信させる力を持っています。
また、最近起きている流行の数々はZ世代から生まれることが多く、SNS上でバズった商品やコンテンツが全国的に拡散し、消費者行動に大きく影響しています。
特に発信力であったり、影響力を持っている人たちのことはインフルエンサーと呼ばれ、インフルエンサーを中心として、情報の発信・拡散が活発に行われています。ごくごく個人的発言がじわじわと話題になり、流行につながるケースも少なくありません。
Z世代はこれからの消費を担う世代として注目すべき存在であり、それぞれ企業でのマーケティング需要が高まっています。
Z世代の消費行動とは……
Z世代は商品を購入するときにSNSで情報収集をする傾向があります。ある企業が行った「Z世代の消費に対する価値観やブランドへの意識調査」では、Z世代に商品・サービスの購入において参考にしている情報源を確認したところ、一位はSNSでした。Z世代の人たちはInstagram、YouTube、X(旧Twitter)、TikTokなど、さまざまなSNSを有効活用して情報収集をしています。
モノ消費よりもコト・トキ消費が行われている
Z世代は、単にモノを所有することにステータスを感じるのではなく、商品・サービスの購入から生じる体験であったり、経験値による「コト消費」、その場所、その時間特有の体験である「トキ消費」を重要視する傾向があります。旅行であったり、アウトドア体験、グルメ、ヨガなどリラクゼーション体験、お稽古事などはコト消費と言っていいでしょう。
トキ消費は、ライブ体験やフェス、コスプレイベント、クラウドファンディングへの参加などです。アーティストが行うライブ配信やオンラインのファンミーティングなども、消費を拡大させている要因です。
コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを重視
多くの情報が過剰に溢れている現代社会において、Z世代の人たちは、コストパフォーマンス(コスパ)やタイムパフォーマンス(タイパ)を重視する傾向があります。デジタル技術の進化によって、より良い情報を短時間で取得することが可能であるため、Z世代は、他の人たちよりも費用対効果、時間対効果を消費活動の中で重視しているのです。
タイパを重要視し、動画を早送りしてみたり、映画を倍速で見る方がいるのもZ世代の特徴です。
商品選考・事前情報収集には時間をかけている
Z世代は、堅実的、保守的な考えを持ち合わせ、商品を購入する際にも失敗しないことを心がけ、じっくり時間をかけて情報収集をし、商品を選別しようとしています。ある調査でも、商品・サービスを購入するときに重視している行動・意識に対して、
・話題性が高い商品・サービスは利用してみたい
・新しい商品・サービスには注目している
という項目は高めであり、商品・サービスを選ぶときに悩む時間が惜しい……という項目は他の世代よりも低いという結果が出ています。
Z世代は、タイパを重要視する一方で、しっかりと時間や労力をかけて情報を収集し、自分自身に最適なモノを選別しているのです。
個性・自分らしさを重視するため、自分自身が好きなものや欲しいものには妥協はしません。「推し活」という言葉が頻繁に使われているように、自身の好きな人やモノ、コトに対してはお金を惜しむことなく使う傾向があります。
Z世代だからこそ体験できる仕掛けを作る
企業は、Z世代に対してコト消費・トキ消費を重視しつつ、楽しんでもらえる広告を作るよう心掛けるといいでしょう。紙媒体のカタログやダイレクトメールを読み物として楽しめるようにすることもいい戦略ですし、診断コンテンツを記載するなど、それぞれ顧客のニーズに合わせて、紙媒体ならではの体験できる仕掛けがあれば、かなりいい効果を期待することができます。
Z世代の心をつかむようなアクションを仕掛けることができれば、やがてSNSで拡散され商品購入やサービスの認知につながり、利益アップを実現することが可能です。
推し活に使用できるコンテンツにする
Z世代の多くの人たちが推し活をしており、ファッションや化粧品、学びに対しても推しが影響しているようです。であれば、企業は、Z世代×推し活をマーケティングに有用し、推し活に使ってもらいやすいコンテンツを企画するといいでしょう。たとえば、ポストカードであったり、表面をコーティングした素材に推しキャラなどをプリントすることで、コンテンツの保存性を高められる上、SNS上で拡散してもらいやすくすることができます。
デジタルとアナログの融合を意識する
よりマーケティング効果を高めるには、紙媒体ばかりを意識するのではなく、Z世代が慣れ親しんでいるデジタルの組み合わせを模索しましょう。デジタルと紙媒体の敷居を取っ払い、SNSやネット広告、イベントや展示会の開催、チラシ・ダイレクトメール発送などを組み合わせ、あらゆる施策を融合させ、相乗的マーケティングを行うようにしてください。まとめ
それぞれ企業がマーケティングを行う上で、Z世代に対してのアプローチはとても大事な課題です。Z世代をターゲットにすることで、よりSNSの拡散効果も期待することができます。ただし、Z世代だから、デジタルマーケティングだけを仕掛けていかなければならないと考える発想には間違いがあります。Z世代だからこそ、紙媒体のダイレクトメールを心に響かせることができます。
紙媒体ならではの特別感を強調し、デジタルなど他施策との融合することによって、Z世代に刺さるマーケティングを検討してみましょう。
アドレス通商では、推し活グッズや各種スポーツチームの会員証、入会特典グッズ、ファンクラブグッズ、などさまざまなDM・商品の発送をおこなっております。
ご興味がございましたら、是非、お問合せ下さい。