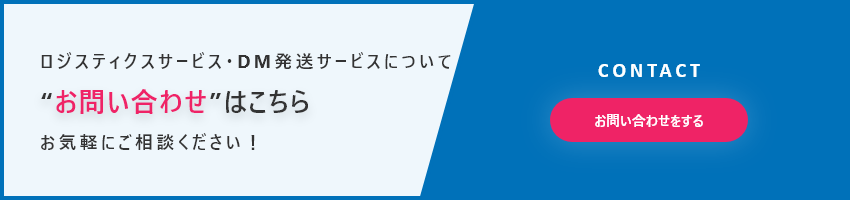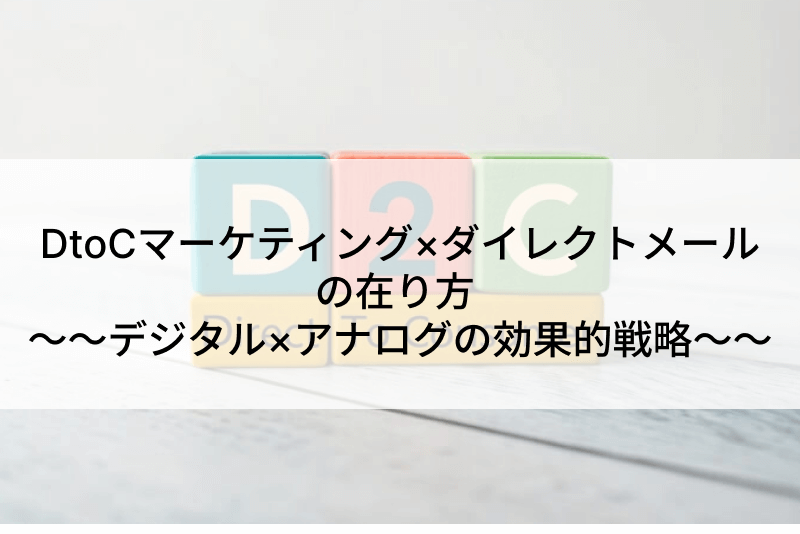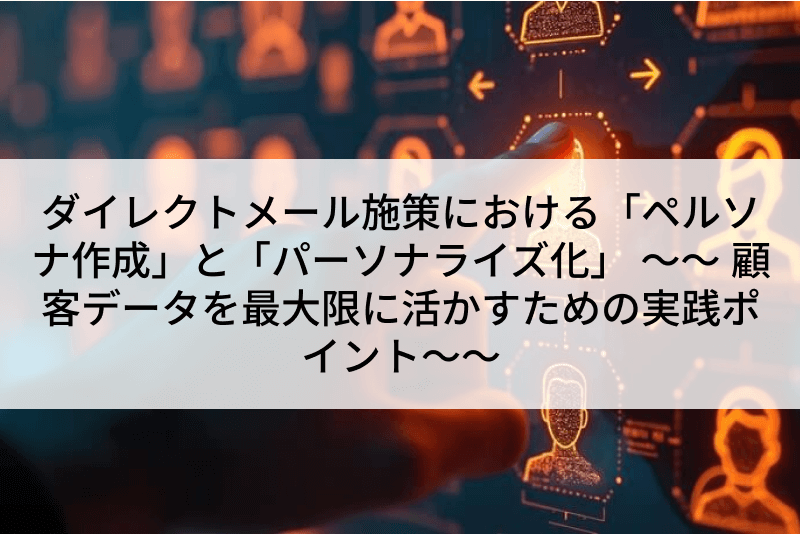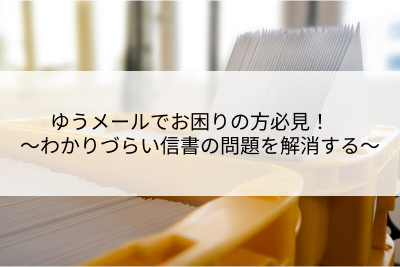
ヤマト運輸でクロネコDM便(旧クロネコメール便)が2023年12月に廃止されております。実は、旧クロネコメール便の廃止に、「信書」が大きく関係しています。
企業で仕事をしている方々は、この「信書」がなんであるのか正しく理解することができているでしょうか。
企業や個人で、信書の扱いを、適当に行っているケースを散見します。
また、信書がなんであるかわかりづらいため、正しい対応をしようと思っても間違えてしまっているという声も多くあります。
信書がわかりづらい問題は、ヤマト運輸と日本郵便とのいわば30年戦争にもあるようです。
クロネコDM便(旧クロネコメール便)が廃止になりお困りの方やゆうメールで発送しようと思ったDMが信書に該当し発送出来ないとお困りの方は、ぜひご一読下さい。
目次
ヤマト運輸における信書の問題点を明らかにする
ヤマト運輸でクロネコメール便が廃止されて既に相当な月日が経過しているのですが、なぜ、クロネコメール便が廃止されたのかといえば、信書の定義がわかりにくく、利用する方々が信書を発送してしまうことで罪に問われるリスクがあることを、ヤマト運輸自体が公表しています。そして、ヤマト運輸では、その状況はいまだ改善されているわけではないとも話しています。
<参照:ヤマト運輸 信書における問題点>
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/ad/opinion/shinsyo/
それ程までに信書の問題はわかりづらいと言ってもいいのかもしれませんが、だからこそ企業や個人の方々は、より信書に対しての正しい認識が必要です。
信書の問題は依然放置されたままである
「信書」とは……、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、また、事実を通知する文書」のことを言います。これは、郵便法第4条第2項によって取り決めされているルールです。<参照:総務省 信書の送達についてのお願い>
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/ad/opinion/shinsyo/
<参照:総務省 信書の定義について>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000447206.pdf
しかし、信書の概念自体曖昧な内容基準であるため、同じ文書だとしても、送付する状況であったり、文章の内容のわずかな違いによって、信書となったり、そうではなくなったりすることがあります。
そこでヤマト運輸では、信書に該当するか否かを利用する方々の誰もがすんなり理解できるように、信書の範囲を封筒の大きさでわかりやすくする外形基準を導入しましょう。という提案をし、総務省 情報通信審議会 郵政政策部会に案の提出をしています。
しかし、残念ながら出された提案について充分な議論もなされることはないまま、情報通信審議会の中間審議において、外形基準の状態では、憲法上保障されている通信の秘密などを合理的に維持することができない。また、現在、宅配便事業者が送付可能なものが可能でなくなる事態が起こる可能性があり、市場の活性化につなげることができない……と言った見解が示されています。
その後、最終答申でも結局は充分な議論がされているとは言い難い面があり、2016年7月に発足した総務省の「郵便のユニバーサルサービスに係る課題等に関する検討会」においては議題にも上がることはありませんでした。
そもそも政府では、信書便の市場において利便性がより向上されるため、わかりづらい信書の定義を、日本の方々全員がすんなりわかる基準へと変えるよう、改正へ向かい議論を続行すべきであるのですが、残念ながら、それがいまだされていないのが現状だと言っていいでしょう。
たとえば、同じ履歴書の発送であったとしても、応募する方々が企業に発送する場合、それは信書の扱いになります。しかし、企業から応募者に返送される履歴書の場合は、信書ではなくなってしまうのです。
「ああ、そういうものか……」という感じで把握できないことでもないのですが、そもそも信書とは現状、それ程までに納得できないものであり、このままの状態にしておくのではなく、なんらかの対応が求められているはずです。
信書はわかりづらいうえ、発送する人が罪に問われる可能性がある
信書がなんであるか、わかりづらく、なかなか理解がされていない現状があるのですが、企業の方々も、個人の方々もだからと言って、軽視できる問題ではありません。
それは、郵便や、信書便以外の方法で信書を発送した場合には、運送事業者だけでなく、送り主の方々も罰せられてしまうからです。ですから、より信書に対して慎重な対応が求められています。信書を間違えて発送したばかりに、企業では大きな信用を失ってしまうこともあるでしょう。
現段階では、送り主の方々が、わかりづらい信書の問題を正確に理解しなければなりません。
日本郵便ではわかりやすいシステムが提供されているのか
それでは、「日本郵便」では、信書についてわかりやすいサービスが提供されているのでしょうか……。その答えも、実はそうではありません。
たとえば、現在「ゆうパケット」を利用して信書を発送することができると思っている方々も多いようです……。
ゆうパケットは、荷物を運ぶサービスであるため信書を送ることはできないのですが、一方で対面での内容物確認など、あらかじめ事務手続きをしないでも郵便ポストへ投函することが可能なため、利用する方々は、ゆうパケットなら信書も発送できると誤解しているケースが多くあります。
2016年に日本郵便において、個人向けサービスである「ゆうパケット」が発売されたことで、意図しない郵便法の違反によって国民のみなさんが罰せられる恐れがより高まったと言っていいでしょう。
このような感じで、日本郵便が提供しているサービスであったとしても、利用する方々に誤解される要素は沢山あるため、日本郵便でも、誤解されないための改善策が必要です。
また、最低でも、送り主への罰則規定は廃止されるべきだという考えはここにもあり、かつ、ゆうパケットのような荷物を運ぶサービスを郵便ポストで引き受けることを中止するべきだという考えもあります。
日本郵便が提供している「レターパック」「スマートレター」は、信書も非信書も送れるサービスとして販売されています。
また、「ゆうメール」や「ゆうパケット」は荷物を運ぶサービスで信書は発送NGとなるのですが、郵便事業を運営するための資産として考えられる郵便ポストでの投函が可能です。
信書も非信書も送れるサービスは、貨物市場を侵食するもの、また、民間競争を妨害するものであり、国民の方々の利便性が阻害される恐れがあります。
さらに言えば、郵便ポストで荷物を発送するサービスを引受けることは、郵便事業者としての優遇措置を受け、貨物運送事業へと拡散していることになり、貨物市場の公平公正であるべき競争が阻害されていると言っていいのではないでしょうか。
なんでヤマト運輸のクロネコメール便は廃止されてしまったのか
以前利用していたお客様からは、なんとしてもクロネコメール便を復活して欲しい……というリクエストがいまだたくさんあります。そもそも、利用する方々は、いまだ、なんでクロネコメール便が廃止されてしまったのかわからない……という声も多いです。
ヤマト運輸では、信書の定義が漠然とした内容基準のまま、発送する側と、運ぶ側の両方に対し罰則が設定されている現状では、信書が混在する可能性が否定できないクロネコメール便を扱うことは極めて難しいということを述べています。
そして、民間事業者同士の公平、公正な競争が活性化されないことより、利用する方々の理想に叶ったサービスが誕生しにくい状況にあるということも指摘しています。
公平、かつ、公正な競争条件が提供され、それぞれ企業が切磋琢磨し、より便利なサービスを構築することこそが、国民の方々の利便性を向上し、かつ、日本経済の発展につなげることができる最善の方法なのです。
郵便料金値上げに際して
2024年10月1日から日本の郵便料金が大幅に値上げされました。25グラム以内の定形郵便の場合、84円から110円へと。また、ハガキも63円から85円へと値上がりしました 。また、郵便料金の値上げにともなって、速達やレターパックなどの郵便サービスも値上げとなりました。
値上げの理由として、人件費の増加、再配達によるコスト増などがあげられています。
また、公平公正な競争環境がない状態であるから、特定の事業者の独占にもつながってしまい、国民の方々の利便性の低下を招くとも考えることができるのではないでしょうか。
人気サービスからの撤退という背景には、ヤマト運輸と日本郵便との30年戦争があるとも言われています。終わりなき戦争とも言われているのですが、ヤマト運輸と日本郵便は、協業に係る合意を果し、クロネコDM便(旧クロネコメール便)は廃止、代わりに日本郵便の特約ゆうメールを利用した、クロネコゆうメールとして生まれ変わりました。
しかし、同時に廃止予定で合意していた、ヤマト運輸のネコポスは廃止とならず、ネコポスを継続しながら、日本郵便へクロネコゆうパケットを委託するという競合商品をヤマト運輸が取り扱う事となり、争いが再燃しております。
企業側からすると、本来あるべきの自由性を取り戻し、より利用者が使いやすいサービスの構築が求められます。
まとめ
いかがでしょうか。今後、何かが変わるのかもしれませんが、現状、信書がわかりづらいものであることは事実ですし、信書が発送出来るのは、値上げした郵便か信書便のみです。
そして、罰則は、発送する側が受ける可能性が充分あるため、より理解度を高める必要があります。